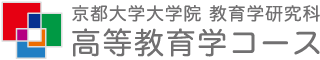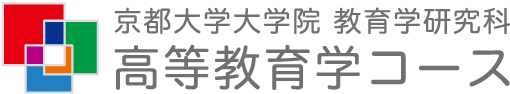教育・学習へのICTの効果的利用
- ここでは、授業内外で利用可能なICT*のツールやプラットフォームについて紹介し、どのように授業がよりよいものとなったり学生の学びに寄与するかという観点から、それらの効果的な活用について説明します。
- 授業内外でICTを効果的に利用したい方は、「授業内外でのICTの活用」をご覧ください。
- 資料を電子化して学生に配布したい、小テストの採点を効率化したい、受講者全体にメールで案内したい
→1.1 学習マネジメントシステム(LMS)
- ビデオ教材を授業外に活用し、対面講義をよりインタラクティブにしたい →1.2 反転授業
- 授業内外で様々なオンラインの学習支援システムを活用したい →1.3 BYOD
- 教育へのICT利用に関して国内外の事例が知りたい →1.4 ICT利用教育に関するリンク集
- 京都大学における教育・学習のICT活用全体について知りたい方は「CONNECT」をご覧ください。
- 英語によるオンライン講義を世界に向けて配信したい方、その取り組みの概要や現状について知りたい方は、「MOOC」をご覧ください。
- 日本語で学内向けまたは一般公開向けにオンライン講義を配信したい方、その取組の概要や現状について知りたい方は、「SPOC」をご覧下さい。英語での利用も可能です。
- 担当している授業や国際会議、研究成果等を、京都大学オープンコースウェア(OCW)を通じてビデオで国内外に発信したい方は、「OCW」をご覧ください。
- 担当している授業や教育改善の取り組み・アイデア・工夫等を、インターネットで手軽に公開したい方、全国の大学教員の授業改善やFD等の教育改善の取り組みについて知りたい方は、「オンラインFD支援(MOST)」をご覧ください。
* ICT: 情報コミュニケーション技術(Information Communication Technology)
授業内外でのICTの活用
本学で提供されているICT環境や、市販のツール、ウェブサービス等を紹介します。
1.1 学習マネジメントシステム(LMS)
- LMS(Learning Management System)は、日々の授業を支援するために授業科目ごとに設けられるオンライン環境で、授業に関するリソース(教材、配布資料)を共有したり、提出物の集約や採点、掲示板やメーリングリストをはじめ、多くの教育・学習支援ツールを統合的に利用できます。
- 本学では、情報環境機構が学習支援サービスPandAを提供しており、学内の授業で利用可能です。利用マニュアルは情報環境機構のウェブサイトで入手できます。
- 教育におけるICT利用の先進的な米国では、ほぼすべての高等教育機関でLMSが導入されており、その利用率も約60%と、大学の授業においてLMSの利用が日常的になってきています(Dahlstrom et al., 2013, p.23)。2020年度のコロナ禍を契機に国内の大学においてもLMSの導入が一気に進みました。
- 講義資料の提供、学習活動、課題の提出等、授業科目に関する情報を一元的に管理することで、統合的な学習データの分析が可能になります。近年は、LMS以外のウェブ上の学習サービスも、LMSと有機的に連携させる動きが進んでいます。例えば、LTI(Learning Tool Interoperability)という学習ツールに関する国際的な仕様の標準化が進んでいます。
1.2 反転授業
- これまで教室でおこなっていた講義を、ビデオを用いて自宅であらかじめ学生に視聴させ、教室では演習や発展的内容をおこなうという新しい授業形態です。
- 各受講者の前提知識や内容の理解の早さは異なるため、それぞれの学生が各自のペースで内容の理解を進めることができます。毎回の授業の開始時に、ビデオの内容の理解度を確認するために小テストをおこなう場合もあります。
- 反転授業は、大きく分けて、次の2種類に分類されます。「完全習得学習型」は、「早い時点で学習者の評価を行い、理解していない生徒に特別な処遇を与えることによって、全員が一定基準以上を理解することをめざす教育方法」であり、「高次能力育成型」は、「アクティブラーニングと呼ばれる読解・作文・討論・問題解決などの活動において分析・統合・評価のような高次思考課題を行う学習」です(バーグマン・サムズ, 2014, p.8-10)。
1.3 BYOD(Bring Your Own Device)

- 「PC必携化」とも言われ、大学に各学生が自分のノートPCやタブレット端末等を持参し、学習活動や大学生活に活用することを言います。
- 授業に各自のPCを持ち込むことで、学生はLMSや他の学習支援サービス、インターネット上の情報や関連文献にアクセスしながら学習を進めることができます。将来的には学習データの分析等により、学生に対して必要な情報や助言を提供する環境が実現可能となります。
- 2020年度のコロナ禍を契機に本学においても学生が所有するノートPCを使ったオンライン授業が実施されました。BYOD環境の充実に向け、無線LAN環境の整備のほか、PC必携化を前提とした教室環境の整備が進められています。
1.4 ICT利用教育に関するリンク集
(国内)
・大学ICT推進協議会(AXIES)
日本の高等教育機関のICT利用の推進機関です。ICT利用教育に関するカンファレンスが年次開催されています。ICT利用教育やMOOC、BYODに関する全国調査の報告書が公開されています。
・国立情報学研究所 大学等におけるオンライン教育とデジタル変革に関するサイバーシンポジウム「教育機関DXシンポ」
国立情報学研究所が主催するオンライン教育やデジタルテクノロジに関するシンポジウムです。コロナ禍を期に定期的に開催されており、過去のアーカイブ動画や報告資料にアクセスできます。
(海外)
・EDUCAUSE
高等教育機関のICT利用の推進機関です。米国の高等教育における教育実践に関する記事が日々更新されています。
・MERLOT
カリフォルニア州立大学システムが運用するオンライン教材の作成・共有サービスです。膨大なリソースから自分に合った教材を検索できます。
・OpenStax
ライス大学が立ち上げた教育プラットフォームです。大学レベルの無料の電子教科書が提供されています。
・LabXchange
科学教育のためのオンラインコミュニティサイトで、ビデオ教材、シミュレーション、クイズ等、多数の教材を個人やコミュニティで無償で利用することができます。本学のMOOCより動画コンテンツを提供しています。
ICT活用教育のためのポータルサイト(CONNECT)
2.1 CONNECTとは
- ポータルサイト「CONNECT」は、2017年5月に公開されました。京都大学のICT(情報コミュニケーション技術)を利用した教育コンテンツ(MOOC、SPOC、OCW、講義ビデオ、教材等)を制作・活用するための情報を提供しています。
- 「MOOCやSPOCって何?どのようにして作成するの?」「OCWにはどのようなコンテンツが掲載されているの?掲載のためには何をすればいい?」…こういった情報をわかりやすく掲載しています。
- また、学内でICTを効果的に活用されている京都大学の先生方へのインタビューや、国内外のICT活用のトレンドを紹介するミニコーナーなども充実しています。
2.2 お問い合わせ先
CONNECTに関するご質問や、京都大学のICT活用教育に関する意見、ご質問、情報提供は、下記お問い合わせフォームからお寄せください。
オンライン/ハイブリッド型授業に関する情報提供サイト(Teaching Online@京大)
3.1 Teaching Online@京大とは
- Teaching Online@京大は、オンライン授業やハイブリッド型授業に関する情報を、主に京都大学の先生方・職員に向けて提供するサイトです。2020年春に2.1 CONNECT内に構築されました。
- 「オンラインでもできること・オンラインだからできること」というキャッチコピーのもと、オンライン/ハイブリッド型授業の実施方法や、その実施に関連した知識(例えば、著作権の問題や、学生への連絡内容、学生とのコミュニケーションの取り方、TAとの連携方法、試験・評価の実施方法など)を幅広く紹介しています。
3.2 お問合せ先
Teaching Online @京大に関するご質問、オンライン授業・ハイブリッド型授業を実施する上でのご相談・ご質問(学内限定)は、以下にお問合せください。
TeachingOnline [at] highedu.kyoto-u.ac.jp([at]を@に変えてください。)
MOOC (大規模オープンオンライン講義)
4.1 MOOCとは
- MOOCは、インターネットを通じて配信される、無償または安価で受講できる講義です。世界中から数千〜数万名が受講登録し、受講者は講義ビデオやオンラインテストなどを通じて学習を進めます。また、大学の講義と同じように、数週間〜数ヶ月かけて受講し、受講期間終了後、一定の成績を収めた合格者には修了証が発行されることもあります。
- OCWとの違いは、通常の大学の講義のように一定期間が設けられて開講すること、課題や試験が課されること、合格者には修了証が発行されることなどがあります。
- 2012年以降、edX、Coursera、FutureLearnといった英語で配信されるプラットフォームのほか、FUN(フランス)、MiriadaX(スペイン)、XuetangX(中国)、JMOOC(日本)等、英語以外の言語圏を対象とした「ローカルMOOC」が立ち上げるなど、世界中で多数のMOOCプラットフォームが存在しています。
4.2 京都大学のMOOC
- 京都大学は、2013年5月に日本で初めてedXへの加盟を発表しました。edXは、MITとハーバード大学が中心となり設立された、世界トップレベルの大学で構成されるMOOCプラットフォームです(本学は、50のチャーター校の一つとして参加)。京都大学は、edXを通じ、「KyotoUx」という名称で講義を配信しています。
- 本学の第3期中期目標・中期計画にはMOOCやOCWの推進が掲げられています。また、スーパーグローバル大学創成支援事業や、本センターの教育コンテンツ活用推進委員会とも連携し、今後も多くの講義を配信していく予定です。
- edX
- KyotoUx提供講義(edX)
4.3 MOOCで講義を配信するメリット
- あなたの講義に、世界中から大勢の受講者が参加します。世界中の優秀な学生を特定し、好成績を修めた受講者には、留学の対象者として直接アプローチすることもできます。
- いったんオンライン上で講義コンテンツを作成すると、学内の学生の予復習、ブレンディッド学習や反転授業の教材としても活用できます。
- 講義コンテンツを開発する過程で、インストラクショナル・デザイン等の観点からアドバイスを受けることができ、より魅力的な授業となります。
- 京大の教育を世界に向けてアピールすることに貢献できます。
4.4 MOOCの活用事例
- 【反転授業】学内の講義の受講者が同時並行でMOOCを受講することによって、授業中はより発展的な内容を扱ったり、グループワーク等の時間に充てることができます。全学共通科目で、上杉教授は「The Chemistry of Life」を反転授業に利用しています。
- 【補習教材】特定の講義ビデオを、授業を休んだ学生に見せたり、予復習用の教材として活用できます。
- 【マイクロマスターズ】edXが提供する修士レベルの教育プログラムです。職種に応じた複数の講義がプログラムとして提供されており、希望者は実際の大学の単位として読み替えることも可能です。企業とも連携し、その成果を就職に活かすことができます。例えば、MITのサプライ・チェーン・マネジメント分野の教育プログラムの修士号取得のうち、半分をedXで受講できます。
Learn more about the MITx MicroMasters
- 【アリゾナ州立大学グローバルフレッシュマンアカデミー】アリゾナ州立大学では、初年次の講義をedXで提供を始めました。2015年8月に「Introduction to Solar Systems Astronomy」提供開始しています。
Learn more about Global Freshman Academy of ASU
4.5 MOOCの配信を希望される方へ
- 個人的あるいは部局などでMOOCの配信をご希望の場合は、下記のお問合せ先までご連絡ください。
- 教育コンテンツ活用推進委員会を通じても問い合わせ対応しています。
4.6 お問合せ先
MOOCに関するご相談、ご質問は下記のメールアドレスへお願いします。
kyotoux[at]highedu.kyoto-u.ac.jp(※[at]を@に変換してお使いください)
SPOC(Small Private Online Courses)
5.1 SPOCとは
- MOOCが全世界に開かれたオンライン講義であるのに対し、MOOCと同様のツールや仕組みを利用し、各大学が自学の学生向けに提供するオンライン講義・教材・学習環境を総称してSPOC(Small Private Online Courses)と呼び、世界的に注目が集まっています。
- SPOCでは、大学固有の目的やニーズに応じた講義や教材を制作し、特定の受講者に向けてオンライン講義を配信したり一般公開することができます。反転授業や予復習のための学習環境を学生に提供したり、課題ツールにより学生の理解度が確認できるなど、多くのメリットがあります。
5.2 京都大学のSPOC(KoALA)

- 本センターでは、京都大学におけるSPOC環境として、KoALAを運用しています。一部の講義は一般公開されており、どなたでも受講できます。edXのプラットフォーム自体がオープンソース化された “Open edX” を利用しているため、edXで提供する講義教材との互換性があります。
5.3 KoALAで講義を配信するメリット
- 講義ビデオや課題等の教材を、反転授業や予復習のために学生に対して提供できます。合格基準に達した受講者には修了証を発行することができます。また、学生の学習進捗状況を随時モニタリングすることができます。
- edXと異なり、講義ビデオのみや課題のみ、といった授業で使う教材の一部のみの提供も可能です。一度教材を制作すれば、以降の講義配信は必要に応じて教材の追加・修正をするだけで構いません。
5.4 KoALAでの配信を希望される方へ(学内限定)
- 個人あるいは部局などでKoALAでのオンライン講義の配信をご希望の場合は、下記のお問合せ先までご連絡ください。
- 教育コンテンツ活用推進委員会を通じても問い合わせ対応しています。
5.5 お問合せ先
KoALAに関するご相談、ご質問は下記のメールアドレスへお願いします。
koala[at]highedu.kyoto-u.ac.jp(※[at]を@に変換してお使いください)
OCW (OpenCourseWare)
6.1 OCWとは
- OCWは、学内で正規開講されているすべての講義を無償公開することを目標に、MITが開始した取り組みです。講義ビデオ、講義ノート、シラバス、小テスト、試験、シミュレーション教材など、MITでは2,500を超える講義が公開されています(2020.6現在)。
- MITが2003年に開始して以降、世界中にOCWを提供する大学が増加し、Open Education Globalという国際的なネットワークに成長しています。
- OCWと通常の大学の授業との違いは、単位が出ないことや、教員に質問できないことなどがあります。
6.2 京都大学のOCW
- 京都大学は、講義ビデオや講義ノート、研究会やシンポジウム、講演会などを、OCWを通じて学内外に向けて配信しています(2005年〜)。京都大学のOCWには、こちらからアクセスできます。映像などの資料はすべて無料です。
- 学内の学生、教職員、他大学の学生、関連学会の研究者、京都大学を志願する高校生、さらなる学習を志す社会人など、あらゆる方々に京都大学の講義内容を知ってもらい、門戸を広げることを目的としてOCWを提供しています。また、国内のみならず世界へ向けて、京都大学のビジビリティを高め、人類の知的資産への貢献と共有を目指しています。
6.3 OCWを利用するメリット
(教員)
- 授業の予復習のための学習リソースを学生に提供できます
- 授業を受ける前に講義ビデオを学生に見させることで、反転授業に活用できます
- 自分の授業を客観的に見ることで、授業改善にもつながります
(学生)
- 授業を受ける前に内容が見られるので、ミスマッチがなくなります
- 繰り返し視聴できるので、試験対策に利用できます
- 時間割が重なっていて受講できなかった授業も視聴できます
- 自分に合う先生や、自分にぴったりの研究分野を発見できます
6.4 OCWの活用事例
- 国際高等教育院の数学教室では、数学(行列)のテキストと10 本の講義ビデオをOCWで配信しています。高校の新カリキュラムで扱われなくなったベクトルや行列についての内容をカバーしており、学生が自習することを前提に制作されました。
- カリフォルニア大学アーバイン校では、化学分野のOCWでの講義ビデオを利用し、カリキュラムと連携し学年別に編集した「OpenChem」を提供しています。テストや問題のサンプルにもアクセスできます。学内の学生だけでなく、誰もが視聴できます。
- 京都大学のOCWでは、講義以外にも、最終講義、分野の紹介ビデオ(例:生命科学研究科)、オープンキャンパス、国際会議等のコンテンツも随時配信しています。
6.5 OCWの配信を希望される方へ
6.6 お問合せ先
OCWに関するお申込み、ご相談、ご質問は下記のメールアドレスへお願いします。
request-ocw[at]highedu.kyoto-u.ac.jp(※[at]を@に変換してお使いください)
オンラインFD支援(Course Collaboration Tools (MOST))
7.1 MOSTとは
- 授業改善や教育改善の知識や経験、ノウハウなどを教員コミュニティで共有するために構築したサイトです。これまで作成された250以上の授業実践やFDの取り組みを誰もが閲覧できるほか、サイトに登録すれば、自身の取り組みについてマルチメディアポートフォリオを作成、公開することができます。
- マルチメディアポートフォリオ(スナップショット)は、KEEP Toolkitというオンラインツールを使って作成します。授業科目、カリキュラム、FD等、用途別にテンプレートが用意されており、直感的に操作しながら簡単にスナップショットを作成できます。
- 作成したスナップショットは、一般公開することも、ある教員コミュニティで限定的に共有することもできます。
- MOST Galaxyではこれまで作成されたスナップショット群を閲覧できます。MOST Tourでは、各テンプレートの利用方法や作成事例、マニュアルにアクセスできます。
- MOSTは元々、米国カーネギー教育振興財団のプログラムに着想を得ており、本家サイトでは、英語による多数のスナップショットのアーカイブにアクセスすることができます。
- MOST
7.2 MOS宝(モストレジャー)
- 大学教員であれば誰もが持つ、授業に関する小さなアイデアやノウハウ、ティップスを、手軽にオンラインコンテンツ化し、教員コミュミニティで共有するためのサイトです。
- コンテンツの作成にあたり、授業実践の文脈をいったん切り離すことで、学問分野や所属機関といった文脈にとらわれず、多くの大学教員が気軽に利用しやすいことが特徴です。
- 作成されたコンテンツを使った実践報告を投稿することにより、教員間で情報交換したり、新たなアイデアを共有することができます。
- MOS宝
7.3 MOSTを利用するメリット
- テンプレートを使うことにより、授業改善やFDの取り組みについてスナップショットを作成する過程で、その取り組みについて客観的に検討したり振り返ることができます。例えば、「コースポートフォリオ」用のテンプレートには、ある授業科目を対象にした検討項目が提示されており、それに回答していけばスナップショットが完成する仕組みになっています。
- 複数の教員で同じテンプレートを使えば、授業間の比較・検討をおこなうことができます。学科全体でスナップショットを作成し、カリキュラム改訂のリソースとして活用された事例もあります。
- スナップショットを定期的にアップデートすることで、授業改善や教育改善について経年変化等を簡単に追うことができ、次の改善点の検討がしやすくなります。
7.4 活用事例
- 毎年、全国から10名程度の大学教員を募り、教員コミュニティで授業改善をおこなうMOSTフェローシッププログラムを提供しています。各教員は、1年間かけて実施する授業改善のプロセスについて対面やオンラインで共有し、その成果をスナップショットとしてまとめて一般公開します。本学教員からの応募もお待ちしています。
- MOSTフェローシッププログラム
- ある大学の理学療法系学科において、学科に所属する全教員がカリキュラム改訂を目的としてコースポートフォリオを作成しました。数回のワークショップで各科目のコースポートフォリオの記載項目を比較・検討し、カリキュラム改訂に活かされました。
- 関西地区FD連絡協議会の加盟校を対象に、組織的に行われたFDの取り組みに関するポスター発表の原稿をスナップショットとして一般公開してきました。これまでの約100件のアーカイブにアクセスし、FDの取り組みへの参考資料にできます。
- FD活動報告会
7.5 お問合せ先
MOSTに関するご相談、ご質問は下記のメールアドレスへお願いします。
most-f[at]highedu.kyoto-u.ac.jp([at]を@に変換してお使いください)
(文献)
Dahlstrom, E., Walker J.D. and Dziuban. C. (2013). ECAR Study of Undergraduate Students and Information Technology (Research Report), Louisville, p.23. CO: EDUCAUSE Center for Analysis and Research, available from http://www.educause.edu/ecar
バーグマン, J., サムズ, A., 山内祐平 (監訳) (2014). 反転授業. オデッセイコミュニケーションズ.(原著: Bergmann, J. & Sams, A. (2012). “Flip Your Classroom: Reach Student in Every Class Every Day,” ISTE and ASCD.)