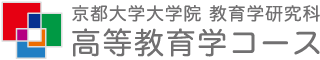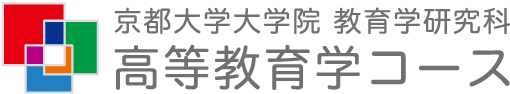大学院生の紹介
森山 寛Hiroshi MORIYAMA
| 学年 | 博士後期課程3回生 |
|---|---|
| 関心領域 | 人文・社会科学系大学院, 大学院教育, 修士課程, 私立大学, キャリア選択 |
| 研究テーマ | 人文・社会科学系大学院修士課程に求められる役割に関する研究 |
| 所属学会 | 大学教育学会, 日本キャリア教育学会, 高等教育学会 |
| 学位論文 | 森山寛. 大学院修士課程への進学決定プロセスと影響要因について ―私立大学大学院の人文社会科学系に着目して―. 京都大学教育学研究科修士学位論文, 修士(教育学). 2022年3月取得 |
梅川 紗綾Saya UMEKAWA
| 学年 | 博士後期課程3回生 |
|---|---|
| 関心領域 | 通信制大学、メディア授業・面接授業、キャンパスライフ |
| 所属学会 | 日本教育工学会,大学教育学会,日本通信教育学会 |
| 学位論文 | 梅川紗綾.大学教育におけるオンライン授業の可能性―コロナ禍における大学教員の体験談の分析から―.桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科修士学位論文,修士(大学アドミニストレーション),2022年9月取得 |
| 学術雑誌 | <査読あり> |
【査読なし】
・梅川紗綾・田口真奈(2024)通信制大学におけるメディア授業は面接授業を代替するか―放送大学におけるメディア授業導入の経緯の調査による一考察.日本教育工学会2024年春季全国大会講演論文集,615-616.
・梅川紗綾・田口真奈(2024)通信制大学における若年層専業学生の入学動機―広報媒体の学生の声の分析から―.第30回大学教育研究フォーラム発表論文集,116.
・松下佳代・奥村百香・田中孝平・山本達也・岡田航平・布柴達男・平山朋子・田中一孝・梅川紗綾・澤邉潤(2024)汎用的/分野横断的な能力は育成可能か―学士課程カリキュラムの比較を通して―.大学教育学会第46回大会発表要旨集録,44-45.
・梅川紗綾・田口真奈(2025)通学課程と通信教育課程の教育・学習目標の差異ー併設校の通学課程と通信教育課程のディプロマ・ポリシーの比較を通してー.日本教育工学会2025年春季全国大会講演論文集,35-36.
・梅川紗綾(2025)正課・正課外の大学経験はどの汎用的な能力を育てるか?―日本の大学における学生調査を用いた先行研究からの一考察―.第31回大学教育研究フォーラム発表論文集,35.
八木 理紗Lisa YAGI
| 学年 | 博士後期課程2回生 |
|---|---|
| 関心領域 | 大学教育学, 教育社会学, 主体性, 非正規雇用, 持続可能性 |
| 研究テーマ | 持続可能な大学経営のための大学職員の主体性と雇用形態に関わる研究 |
| 学位論文 | 八木理紗, 大学における職員の雇用形態と主体性の検証 −私立大学職員の多様な働き方を中心に−(修士論文) |
岡田 航平Kohei OKADA
| 学年 | 博士後期課程2回生 |
|---|---|
| 関心領域 | 大学教育学,大学への移行(transition),高校から大学への移行期,高大接続,入学前教育 |
| 研究テーマ | 高校から大学への移行期における高校生・大学生の経験に関する研究 |
| 所属学会 | 大学教育学会,日本教育学会,初年次教育学会,日本カリキュラム学会 |
| 学位論文 | 「高校から大学への移行期における入学前教育の経験—高校生・大学生の語りに着目して—」『京都大学大学院教育学研究科修士学位論文』修士(教育学),2023年3月取得 |
| 学術雑誌 | 【査読有り】 【査読無し】 |
・岡田航平(2022)「アメリカの大学における夏季ブリッジ・プログラムの変遷—日本の入学前教育への示唆を意図して—」『第28回大学教育研究フォーラム発表論文集』132.
・田中孝平・大野真理子・岡田航平(2022)「「探究学習評価型入試」が目指す高大接続の検討—大学における教育的取り組みとの接続をふまえて—」『第28回大学教育研究フォーラム発表論文集』108.
・岡田航平・大野真理子(2022)「学びのデザインの特徴と教員の質保証」(参加者企画セッション「汎用的能力の形成を可能にするもの—ミネルヴァ大学の大学・教員へのインタビューから考える—」で発表)『第28回大学教育研究フォーラム発表論文集』175.
・岡田航平(2022)「入学前教育の意義と課題に関する一考察—入学前教育を経験した高校生の語りを通して—」『大学教育学会第44回発表要旨集録』174-175.
・岡田航平・大野真理子(2022)「教員の学びへの関与と質保証の方法」(ラウンドテーブル「汎用的能力の育成と評価の可能性—ミネルヴァモデルを手がかりに—」で発表)『大学教育学会第44回発表要旨集録』39-40.
・森朋子・溝口侑・常浦光希・岡田航平(2022)「入学前教育をデザインする—ライフキャリア型初年次教育との接続の観点から—」『初年次教育学会第15回大会発表要旨集』29.
・岡田航平(2023)「日本のマス型高大接続・移行の質的検討」(参加者企画セッション「高大接続・移行への新たなアプローチ—日英比較と質的・量的研究を通して—」で発表)『第29回大学教育研究フォーラム発表論文集』140.
・岡田航平(2023)「高校生が抱く大学・大学生へのイメージに関する一考察—大学合格から大学入学までの期間における高校生の語りを通して—」『大学教育学会第45回発表要旨集録』116-117.
・岡田航平(2023)「ボーダーフリー大学への学生の移行に関する質的検討」(ラウンドテーブル「高大移行における学生の移行の多様性」で発表)『大学教育学会第45回発表要旨集録』39-40.
・岡田航平(2024)「大学教職員からみた入学前教育を取り巻く検討課題」『第30回大学教育研究フォーラム発表論文集』98.
・岡田航平(2024)「アウトリーチ活動の特徴」(参加者企画セッション「ミネルバ大学を解剖する—学生へのインタビューを通して」で発表)『第30回大学教育研究フォーラム発表論文集』121.
・岡田航平(2024)「大学入試と大学教育の狭間における経験とその実態—大学合格から大学入学までの期間における高校生の語りを通して—」『大学教育学会第46回大会発表要旨集録』181-182.
・Kohei Okada. (2024). A study of student’s lived experiences in the transition from secondary school to higher education. In Critical University Studies Conference 2024. 98.
・岡田航平(2025)「大学一年前期の学びと生活を踏まえた入学前教育の経験」『第31回大学教育研究フォーラム発表論文集』73.
呉 尚峻Shangjun WU
| 学年 | 博士後期課程2回生 |
|---|---|
| 関心領域 | Critical EMI, Decolonization, Native Speakerism, Global Englishes, Japanese Philosophy, Unlearning |
| 研究テーマ | Unlearning Native-Speakerism through “Double Eyes”: A Critical EMI Intervention in Japanese Higher Education |
| 所属学会 | 日本英語教育学会, ELINET, PESA |
| 学位論文 | The Japaneseness of Japanese English: Thinking through Esyun Hamaguchi’s Contextualism |
| 学術雑誌 | 【査読あり】 【査読なし】 |
・Wu Shangjun (2024), Japanese English as Self Expression. CERC and Kyoto University Joint Round Table.
・Wu Shangjun (2024), The Japaneseness of Japanese English: Thinking through Esyun Hamaguchi’s Conexualism. The 12th European Conference on Language Learning (ECLL2024).
裴 育紅Yuhong PEI
| 学年 | 博士後期課程1回生 |
|---|---|
| 関心領域 | アサインメント(課題, assignment),宿題,授業外学習 |
| 研究テーマ | 高等教育におけるアサインメントの活用とその効果に関する研究 |
| 所属学会 | 日本教育工学会 |
| 学位論文 | オンライン授業における大学生の課題遂行エンゲージメントに影響を与える要因の検討 |
吉川 大樹Daiki YOSHIKAWA
| 学年 | 修士課程2回生 |
|---|---|
| 関心領域 | 教職協働, 大学職員論, スタッフ・ディベロップメント(SD) |
| 研究テーマ | 現場の大学職員の「教職協働観」について−大規模国立大学を例に− |
| 所属学会 | 大学教育学会 |
・吉川大樹(2025)「現場の大学職員の「教職協働観」について—大規模国立大学を例に—」『第31回大学教育研究フォーラム発表論文集』,40.
森本 悠Haruka MORIMOTO
| 学年 | 修士課程2回生 |
|---|---|
| 関心領域 | SD(スタッフ・ディべロップメント), キャリア移行(トランジション), 成人学習, 初等中等教育から大学への接続, 探求学習 |
| 研究テーマ | 大学職員のキャリアトランジションー30-40代の中期キャリア子育て中の私立大学職員を事例としてー |
| 所属学会 | 大学教育学会 |
修士論文・博士論文題目
氏名 |
年度 |
論題 |
| 修士論文 | ||
| 奥村 百香 | 2024 | 学生が語る大学との関わり—解釈学的アプローチによる学生参画再考— |
| Walden S.S. YEUNG | 2024 | ニューノーマルにおける「バーチャル留学」のあり方 |
| Neungmi KIM | 2024 | 創造的思考プロセスを促進する生成AIツールの開発と効果に関する実証的研究 |
| Zhiqi TAN | 2023 | 二極化する留学経験:シドニー大学のビジネス関連学科における中国人学生を事例に |
| 岡田 航平 | 2022 | 高校から大学への移行期における入学前教育の経験-高校生・大学生の語りに着目して- |
| 森山 寛 | 2021 | 大学院修士課程への進学決定プロセスと影響要因について ―私立大学大学院の人文社会科学系に着目して― |
| 佐藤 有理 | 2021 | 日本語学習者のキャリアにみる学習成果 ―日本語・日本研究とエンプロイアビリティの関係に着目して― |
| 中西 勝彦 | 2020 | 単位不足学生の大学生活経験に関する研究 ―単位不足に至る要因とプロセスに着目して― |
| 大野 真理子 | 2020 | 「多面的・総合的評価」を取り入れた大学入学者選抜の課題と支援方法に関する研究― アドミッション業務における専門性に着目して ― |
| 田中 孝平 | 2020 | 高大接続における高校の探究学習の意義と課題 ―大学生対象のインタビュー調査を通して― |
| 周 孝誠 | 2019 | 大学におけるピア・チュータリングを中心とした統合型学習支援機関に関する 研究 |
| 大森 俊典 | 2019 | Disciplinary Literacy の読みの側面に関する質的研究 ―心理学と教育学の 4 領域における比較分析― |
| 梁 琳娟 | 2019 | 国立大学による ICT を活用した留学生の日本語学習支援に関する検討―中国人留学生の日本語学習の実態を踏まえて― |
| 岩田 貴帆 | 2019 | 協議ワークを取り入れたピアレビューの開発と学生の自己評価力向上の効果検証 |
| 澁川 幸加 | 2018 | 反転授業における事前学習への取り組み方に関する調査研究 |
| 杉山 芳生 | 2018 | 医療分野の事例分析に基づく PBL の持続可能性に関する検討 |
| 武田 佳子 | 2017 | 大学生のリーダーシップ自己効力感に関する研究 ―時間と社会性の関係に着目して― |
| 溝口 侑 | 2017 | 大学生のキャリア意識とロールモデルの関係 |
| 河合 道雄 | 2016 | 日本人大学生の留学経験における成果をもたらす行動とその要因に関する実証的研究 |
| 和田 翔二朗 | 2016 | アクティブラーニング型授業における対人関係と学習への取り組み・態度との関連について |
| 飯尾 健 | 2016 | 大学生の学術情報リテラシーの評価- Can-Do table の提案および大学図書館利用の影響の検討- |
| 香西 佳美 | 2016 | MOOC での実践経験を通じた大学教員の授業力量形成- TPACK 形成と意識変容に着目して- |
| 松井 桃子 | 2015 | 大学生の学業適応感とキャリア意識の関連性-適応過程におけるコーピング方略に着目して- |
| 山田 勉 | 2015 | 学生参加による高等教育の質保証-ボローニャ・プロセスにおける<消費者としての学生>の考察を中心に- |
| 丁 愛美 | 2014 | 内容重視型教授法(Content-based Instruction)が大学生の英語学習態度に与える影響に関する実践的研究 |
| 全 京和 | 2014 | 脆弱性を持つ政策領域に対するソフトなガバナンスの適用- EU の教育・訓練政策における「Open Method of Coordination」に焦点をあわせて- |
| 蒲 雲菲 | 2014 | 高等教育における内部質保証システムに関する研究−認証評価報告書の記述に基づいて− |
| 星野 俊樹 | 2014 | Problem-based Learning の導入支援のための汎用的ツールが大学教員の授業設計と実践に及ぼす効果に関する実証的研究 |
| 周 静 | 2014 | 日本語学習者によるピア・ラーニングの有効性−中国の大学での「精読」科目における実験授業を通じて− |
| 田中 正之 | 2014 | 学生の学びと成長に影響を及ぼす友人関係とキャリア意識 |
| 斎藤 有吾 | 2012 | 大学初年次における授業経験が学習へのアプローチの変容に与える影響 |
| 大山 牧子 | 2010 | 大学における授業デザインに関する教員の協調的な学び-アクティブ・ラーニング形態の授業を対象に- |
| 蒋 妍 | 2010 | 大学生の授業・授業外学習観と達成動機・将来展望・意欲低下との関連-授業・授業外学習観タイプによる検討- |
| 畑野 快 | 2010 | アイデンティティの観点からみた大学生の学習動機と学習行動 |
| 本部かの子 | 2009 | SoTLという理念に見る教えることと学ぶことの関係 |
| 丘 恩卿 | 2009 | 大学生の英語学習における学習方略の変容とその効果 |
| 河井 亨 | 2009 | 大学生の学習におけるコミュニティ・ブリッジング |
| 平山 朋子 | 2006 | 理学療法士養成の臨床実習における二重の応答性の生成 |
| 門田 久美子 | 2006 | 現代における「教養」の意味転換-読書と教養の関係の再構成- |
| 王 霞 | 2004 | 大学評価における大学の自律性と説明責任―京都大学の大学評価の実情を通して― |
| 杉原 真晃 | 2003 | 大学授業における学びのコミュニティの形成一教養教育でのアイデンティティの探求過程に着目して一 |
| 保田 正樹 | 2001 | 高等教育研究の学問論 ―「ミクロ」と「マクロ」の葛藤から対話へ― |
| 博士論文 | ||
| 大野 真理子 | 2024 | 大学入学者選抜における多面的・総合的評価の解釈と実践—組織学習の観点からの事例研究— |
| 松尾 美香 | 2024 | 大学における冒険教育の実践とその教育効果 |
| 袁 通衢 | 2024 | 中国の大学生の授業外日本語学習における自律的なOER利用の支援に関する実証的研究 |
| 田中 孝平 | 2023 | 高校の探究学習を通じた高大接続に関する研究 ―移行についての学生の語りの分析にもとづいて― |
| 岩田 貴帆 | 2023 | 自己評価に基づく自律的なパフォーマンス改善を促す教授法の開発―学生主体の評価活動を取り入れた授業実践を通して― |
| 香西 佳美 | 2023 | プレFDを通じた大学初任教員の授業力量形成の課程と支援に関する研究 |
| 鄭 漢模 | 2022 | 公開大学モデルの形成に関する研究 |
| 澁川 幸加 | 2022 | 深い学習を促す反転授業設計に関する実証的研究―学生への事前学習支援と教員への授業設計支援に着目して― |
| 杉山 芳生 | 2021 | 大学教育における PBL の問題と可能性 |
| Nikan Sadehvandi | 2019 | An Empirical Study on the Effects of Pedagogical Intervention on Improving the Quality of Peer Assessment in Massive Open Online Courses |
| 谷 美奈 | 2019 | 「書く」ことによる学生の自己形成 ―文章表現「パーソナル・ライティング」の実践を通して― |
| 辻 香代 | 2019 | 母語使用を取り入れた外国語ライティング教育に関する研究 |
| 山田 勉 | 2018 | 学生参加による高等教育の質保証―「欧州高等教育圏における質保証の基準とガイドライン」に関する批判的考察に基づいて― |
| 斎藤 有吾 | 2017 | 学士課程教育における高次の統合的な能力の評価とその変容に寄与する学習者要因の検討― コースレベルの直接評価と間接評価の統合 ― |
| 小山 理子 | 2017 | アクティブラーニング型授業の学習成果に関する研究 |
| 大山 牧子 | 2016 | 大学教育における教員の省察プロセスのモデル化に関する研究 |
| 平山 朋子 | 2016 | 理学療法士教育におけるパフォーマンス評価と学生の学びに関する研究―OSCE リフレクション法の開発・拡張とその有効性の分析― |
| 蒋 妍 | 2015 | 大学生の授業外学習を促す要因に関する検討-授業内・授業外学習観に着目して- |
| 畑野 快 | 2013 | 大学生の主体的な学修態度の形成に関する実証的研究 |
| 河井 亨 | 2012 | 授業/授業外にわたる大学生の学習ダイナミクスについての研究-ラーニング・ブリッジングの検討- |
修了生の進路
| *は研究指導認定退学 **は中途退学 |
(2025年4月時点) | |
修士/博士後期課程 |
修了/退学年度 |
現在の所属 |
| 博士後期課程 | 2024 | 東北大学アドミッション機構 |
| 修士課程 | 2024 | 学校法人立命館職員 |
| 博士後期課程 | 2024* | アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター |
| 博士後期課程 | 2024 | 対外経済貿易大学外国語学部(中国) |
| 修士課程 | 2023 | Amazon Japan |
| 修士課程 | 2021 | 立命館大学 教学部大学院課 |
| 修士課程 | 2020 | 京都文教大学 総合社会学部 総合社会学科 |
| 修士課程 | 2019 | 上海尋夢信息技術有限公司(Pinduoduo) |
| 修士課程 | 2019 | 株式会社ホープス |
| 修士課程 | 2017 | 株式会社LITALICO |
| 修士課程 | 2017 | 桐蔭横浜大学 教育研究開発機構 |
| 修士課程 | 2015 | 神戸大学 経済学研究科国際交流室 |
| 修士課程 | 2014 | Nothing(中国企業) |
| 修士課程 | 2014 | 学校法人桐朋学園 桐朋小学校 |
| 博士後期課程 | 2024 | 東北大学 高度教養教育・学生支援機構 入試開発室 |
| 博士後期課程 | 2023 | 北海道大学 高等教育推進機構 |
| 博士後期課程 | 2023 | 関西学院大学 高等教育推進センター |
| 博士後期課程 | 2022 | 中央大学 文学部/教育力研究開発機構 |
| 博士後期課程 | 2021 | 藍野大学 |
| 博士後期課程 | 2021* | 岡山理科大学 教育推進機構 |
| 博士後期課程 | 2020* | 桐蔭横浜大学 教育研究開発機構 |
| 博士後期課程 | 2019 | 大阪公立大学 国際基幹教育機構 |
| 博士後期課程 | 2016*、2019 | 京都ノートルダム女子大学 |
| 博士後期課程 | 2019* | 徳島大学 高等教育研究センター |
| 博士後期課程 | 2019* | 早稲田大学 大学総合研究センター |
| 博士後期課程 | 2018 | 名古屋市立大学 高等教育院 |
| 博士後期課程 | 2017 | 京都光華女子大学 短期大学部 ライフデザイン学科 |
| 博士後期課程 | 2017~2019在籍 | 三重大学 高等教育開発デザイン機構 |
| 博士後期課程 | 2016*、2019 | 帝塚山大学 全学教育開発センター |
| 博士後期課程 | 2015** | 德勤咨询(广州)有限公司 |
| 博士後期課程 | 2015*、2017 | 新潟大学 経営戦略本部 |
| 博士後期課程 | 2013 | 大阪公立大学 国際基幹教育機構 |
| 博士後期課程 | 2013*、2016 | 大阪大学 全学教育推進機構 |
| 博士後期課程 | 2013*、2016 | 藍野大学 医療保健学部理学療法学科 |
| 博士後期課程 | 2013*、2015 | 早稲田大学 大学総合研究センター |
| 博士後期課程 | 2012 | 立命館大学 スポーツ健康科学部/教育・学修支援センター |
| 博士後期課程 | 2006** | 聖心女子大学 現代教養学部 |